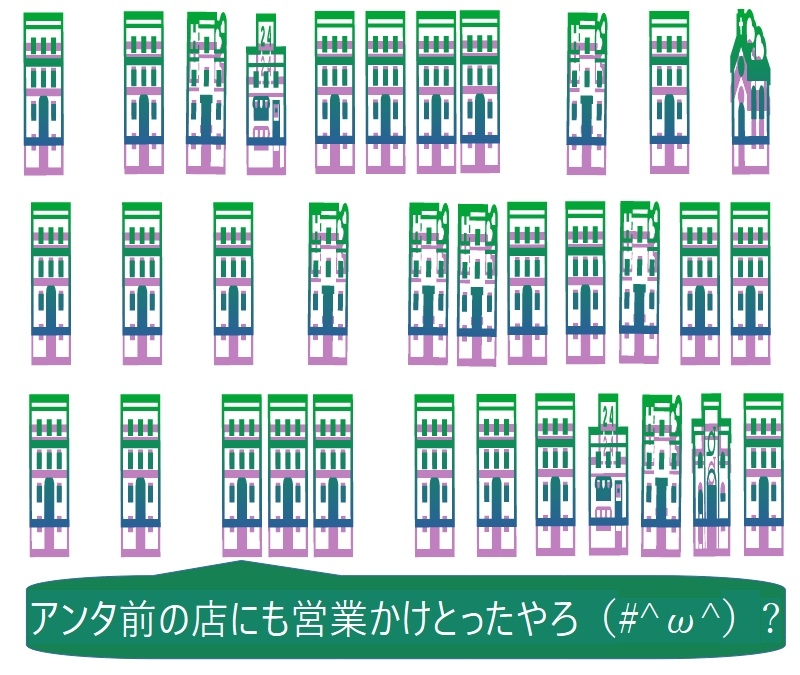介護業界の変なところ駄目なところ13選⓶
変な従事者が多い
写真:佐久島のフリー写真素材より
悪い意味で本当に色々な人がいます。人手が足りないのは分かるのですが、業界知識とか適正がない人を平気で採用します。上記の私の経歴を見て介護業界に詳しくない方は「老人ホームと高齢者向け住宅て違うの?」と思った人もいるかもしれませんが、この違いをまともに説明できる介護従事者はおそらく半分もいないと思います。
その他、極端な例も含みますが以下のような人がいました。
・学や常識がない
検食簿(利用者と同じものを食べて異常がなかったことを記録する書類)に時間を書く欄があるのに空欄にしている人が多く、栄養士から「行政の監査で見られる書類だからちゃんと書いてください」と申し送りがあった時に「「ちゃんと」とか何でこんな強い言 い方されないといけないんだ」と言って「喧嘩売られてる」「挑戦されてる」等と解釈する人が多かった。この件だけでなく、文章の前半だけとか後半だけを読み取っており連絡事項を理解できない人を沢山見ました。
・元販売職の人
販売とか接客で働いていた人が介護に来ることがたまにあるのですが、中途半端に自分の経験を生かそうとしているのか利用者に頼まれたことは何も考えずに引き受けてしまったり、利用者と話をする時には膝をついて話を聞いたりする人がいるんですね。
利用者=お客様と考えて「お客様は神様です」理論で接しているようなのですが、利用者=お客様なのかというのは難しい所があります。というのも、介護保険は保険と呼ばれはするものの財源の半分は税金で、高齢者の保険料では4分の1も賄えていません(残りの30%近くが40歳~64歳の方の介護保険料で賄われているため)。さらにサービス利用負担割合は1割の高齢者が大半なので、純粋にお客様と言って良いのかと考えることが多々あります。
そういう人に限って支援記録記入など行政から義務付けられてる仕事が適当だったりします(一番のお客様やぞと言いたかったがパワハラになりそうなので止めた)。
現在の福祉の理念としてエンパワメントとという考え方があり「利用者ができるようになる/できる状態を保つ」というのが今の福祉の基本となっています。なので、やはり利用者は利用者なので要求されたことでも「できないことはできない」そして「できない理由は〇〇だからです」と介護職員は言えないといけないのですが、結局「お客様なので」で終わらせようとする。
労働者の質が低い
・元ヤーさん
未バレ防止のために詳細は省きます。面接にハーフパンツ、Tシャツという出で立ちで来
て採用されてました。
・仲良しグループだけで仕事する人
女性が多い職場だからでしょうか、仲間内だけで勝手なルール作ってる方々が結構いま
す。同じ仕事の手順でもグループによって言うことが違うのです。現場リーダークラスにどっちが正しいのか確認とるのですが「臨機応変でお願いします」と言われたこと
さえあります。
・1人で仕事する人
そうかと思えば一人で仕事する人もいます。単に黙々と仕事しているだけなら良いのですが、トイレ誘導の時間なのに1人だけ書類作ってる人とか周りが見えない人が結構います。
また、これの派生形かなと思うのですが、自分のやり方をやたら通したがる人がいます。新人が来ると「○○はこうなんです」と自分のやり方を強要して、それが出来なかったり疑問を言うと怒りだす人とかいます。施設長クラスの人に相談したら「あの人はいつもそうで何度も指導してるから言ってくれたらまた指導します」と言われたこともあります。何度も指導受けるような人には新人つけないとか配慮すればと思うんですけど、そういう配慮がないのもこの業界の特徴な気がします。
・日誌で主張する人々
日誌とか日報とか施設によって呼び方はそれぞれですが、その日何があったか等をまとめる記録です。基本的には起ったこと及びそれにどう対応したかという事実を書く書類であり、これは当然に行政による監査の際に見られる書類です。昔は手書きだったのですが、電子カルテのようにパソコンやタブレットで記録するようになり、後から消せるからかたまに自己主張を記入する人がいます。
例えば「〇月〇日〇時〇分 A様より入浴後に腕時計がなくなったと訴えあり、浴室を探すが見つからず。施設長に報告する。」とかあると、それに対して入浴介助した職員が「間違えて一緒に入浴したBさんのカバンに入れていました。すいません。」等と書いていたりします。記録として残すものではないとおもうのですが、謝罪したかったのでしょう。
一番印象に残っている例が最後にいた施設なので身バレの可能性あるため詳細は避けますが、「~だと思います。」という主張に対して「私の意見ではありますが・・・」と返信している人がいました。どっちも副主任クラスです。記録を書く書類で何をしているのだろう?てなりますよね。しかも施設長クラスが注意しないという。
ただ、申し送り欄などがあるタイプの電子日報ですと施設によっては本当に申し送りで使っている場合もあるので場合によっては仕方ない内容もあります。
-寄稿部分はここまで-
キャリアの墓場となっている現状
介護業界の大きな問題としては、やはり介護業界自体がキャリアの墓場となっている面がある。
芸能人の懲罰的な行先として介護業界に流れることが過去にあったが、いかんせん薄給であるが故に「他の業界や職業で通用しなくなった人」が介護に集まっている現状がある。
一つ確かに言えることは、介護業界にも品質管理の手法を取り入れた方が良いということである。
品質管理の手法を取り入れ、介護業界全体が最適化されない限り、こうした問題が解決することはないだろう。